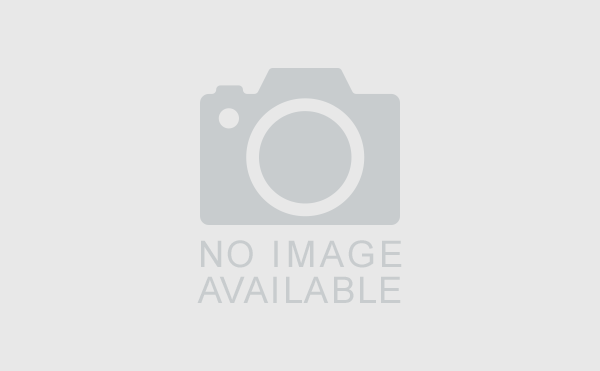Vol.192【学校・公営プールの廃止について】
◇◆◇===========================◇◆◇
川相いい仕事マガジン vol.192
発 行:川相商事株式会社
Kawai Shoji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 https://e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇
=================================
川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
=================================
夏本番を迎え、体温超えの気温となる日も多く、熱中症対策への意識が高まっています。
2025年6月からは、職場での熱中症対策が義務化されることも影響しているようです。
また、自転車の通勤に関しては、2024年11月から罰則が強化され、
2026年4月には青切符の対象となります。
交通違反には反則金が科されますので、ルールの確認をお願いします。
事故防止のためにも、安全運転を意識して行動しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
──────────────────────────────────
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
学校プールの廃止について
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
いつもメルマガをご愛読いただき、どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフでコンサルティングをしています石橋と申します。
現在、学校教育において水泳の授業、つまり学校プールの授業を廃止する動きが
広がりつつあります。
全国の自治体では、「プールや水泳の授業を今後どうするべきか」、
あるいは「廃止するか、外部に委託するか」といった議論が交わされています。
今回は学校プールの廃止について考えてみようと思います。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
プール授業廃止は正しい判断か
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
廃止の理由としてよく挙げられるのは、
プール施設の老朽化による補修費や維持管理コストの問題、
さらには水泳指導中に起こり得る水難事故のリスクです。
特に、教員の中には泳げない人もおり、
そうした状況で安全管理を求められることが負担だという指摘もあります。
こうしたコストやリスクの観点から、
水泳授業は今や小中学校にとって過大な負担ではないかと検討されているのです。
しかし、この問題にすぐに正しい判断を下すことは難しいでしょう。
本当に正しかったかどうかがわかるのは、
もしかしたら50年後、あるいは70年後になって初めて、
「あのときの判断が正解だったか否か」が明らかになるかもしれません。
今回のように何かを「廃止する」と決める場合、その判断には慎重さが求められます。
制度を新たに導入するのは比較的簡単ですが、廃止となると深い覚悟と熟慮が必要です。
だからこそ、制度を廃止する際には「民主的な理由」ではなく、
「トップダウン」で判断されるべきだという意見もあります。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
PL学園野球部の例
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
このテーマを考える上で、私はある象徴的な例としてPL学園を思い出しました。
PL学園といえば、高校野球で圧倒的な強さを誇り、23年連続でプロ野球選手を輩出した名門校です。
この強さを支えていたのが、「付き人制度」と呼ばれる独自の教育制度でした。
しかし、あるときこの制度が廃止され、それを機に野球部は一気に弱体化し、
最終的には廃部にまで追い込まれてしまいます。
この「付き人制度」とは、いわば日本の伝統的な徒弟制度に近いもので、
プロフェッショナル精神や礼儀作法、上下関係の中で学ぶ姿勢を養うものでした。
表面的には時代遅れと捉えられるかもしれませんが、
その本質は人間の内面を育てる教育にありました。
もちろん、こうした特定の制度には負の側面も存在します。
付き人制度においても、閉鎖的で孤立しやすい人間関係の中で、
他者からの目が届きにくくなり、いじめのような問題が生じたとされる場面もありました。
その意味では、制度に内在するリスクは無視できません。
しかし、そうしたネガティブな側面があったからといって、
「良いところも悪いところも一般の人の目にさらされずに、全てを一括して廃止してしまう」
という判断には、大きな問題があるのではないでしょうか。
良い面を育て、悪い面を改善するという視点が欠けていたのです。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
制度の廃止において大事なこと
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
このように、制度の廃止はその場の「利便性」や「効率性」だけで決めてはいけません。
江戸時代末期、「幕末の頭脳」とも称された佐藤一斎は、次のように語っています。
「法は変えるな。しきたりは変えよ。」
つまり、人の心や良心の発達に関わるような「法」は変えてはならない。
一方で、利便性や手続きのための「しきたり」は、時代に合わせて柔軟に変えていくべきだと。
逆に、これを間違ってしまうと、組織は崩壊すると彼は警鐘を鳴らしています。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
まとめ
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
では、水泳の授業はどう捉えるべきでしょうか。
私は、廃止によって失われるものへの評価が、
あまりにも軽く扱われているのではないかと危惧しています。
その背景には、本音として「水泳の授業は面倒」「教員もやりたくない」
といった思いが潜んでいるのではないでしょうか。
たしかに子どもにとっても、プールの授業が苦手という声はあります。
教員の中にも、正直「水着になるのが嫌だ」という理由で避けたいと思っている方も
いるかもしれません。
しかし、そうした本音が制度の廃止に影響しているとしたら、
それは本当に子どもの教育のための判断といえるのでしょうか?
今回の水泳授業の廃止という話題をきっかけに、
「何かをやめるとき」の判断のあり方について、一緒に考えてみたいと思います。
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 石橋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【E-Mail】support@4jh.jp
【電 話】06-6945-5550