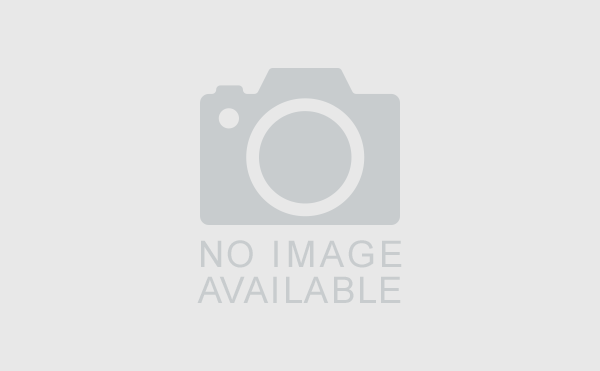Vol.193【最低賃金】
◇◆◇===========================◇◆◇
川相いい仕事マガジン vol.193
発 行:川相商事株式会社
Kawai Shoji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 https://e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇
=================================
川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
=================================
7月に当社上半期の事業報告会があり、大阪本社と滋賀支社の社員が集結しました。
数十年前では、製造業と言えば現場は男性が大半を占めていましたが、
今では、女性も多く働いています。
当社の製造現場においても、男性だけでなく多くの女性が活躍しています。
昭和、平成、令和、時代と共に働く人の仕事観や価値観も大きく変わってきていますが、
戦争があった当時の人の事を想うと、
現在、自由に仕事を選ぶ事ができる私たちは本当に幸せだと気づかされます。
日々の生活や仕事など、当たり前と思っている事に再度、目を向けて感謝しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
──────────────────────────────────
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
最低賃金について
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
いつもメルマガをご愛読いただきありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフでコンサルティングをしています岸田と申します。
今年の最低賃金改定の目安が発表されました。
ここでは過去最高の63円の引き上げが目安とされ、全国平均は1,118円となりました。
また、政府は2030年半ばまでに全国平均を1500円への引き上げを予定しています。
この人件費の上昇にどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
今回は、最低賃金について原稿を進めてみます。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
最低賃金とは?国の狙いはどこにあるか
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
最低賃金は「労働者の生活の安定」と「労働力の質的向上」を目的に設定されています。
しかし近年の引き上げペースは、単に生活水準を守るだけでなく、
経済政策の一環としての意味合いが強くなっていると思われます。
最低賃金の引き上げに、政府は以下のような狙いがあるのではないでしょうか。
1.内需拡大
日本経済は長年「デフレマインド」に苦しんできました。
賃金が上がらないから消費が伸びない、消費が伸びないから投資もしぼむ。
この悪循環を断ち切るため、強制的に消費を増やす仕組みとして最低賃金を上げています。
賃金の底上げをすることによって購買力を上げようと考えているのです。
2.格差是正と社会保障の軽減
低所得層が増えれば、生活保護や各種給付への依存が増えます。
それは財政の圧迫要因となります。
最低賃金を引き上げることで働けば最低限は生活できる社会をつくり、
給付に依存しなくても済む構造を目指しています。
つまり「福祉コストを減らす」狙いが含まれていると考えます。
3.国際比較と投資環境の改善
主要国と比べ、日本の賃金は低くなっており、
国際的な競争力の低下を招いてきたと言われています。
いまは「安いニッポン」という言葉もあります。
このイメージを払拭し、健全な経済循環をつくること。
これも引き上げの理由のひとつと言われます。
またその他、産業淘汰の加速や税収確保も目的として持っていると考えられます。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
短期目線で考える企業の対応
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
最低賃金の上昇により、企業の財務的な圧力、社会の雇用構造の変化が
今後、ますます進んでいくと考えられます。
では、企業はどのように対応していけばよいのでしょうか。
まずは短期目線でできることを見ていきましょう。
○助成金活用(業務改善助成金)
業務改善助成金とは、生産性向上のための設備投資や
システム導入にかかった費用の一部を助成する助成金です。
賃金引き上げ要件がありますが、要件に合えば
最大600万円が助成されます。
注意点は、着金まで時間がかかることです。
最初に交付申請の書類の審査(2~3か月程)が通った後、
設備導入を行い、そのあとに実績報告を行う流れになります。
※交付申請の書類の審査完了前に設備導入をしてしまうと受給できません。
また、助成金は条件に合えばよいのですが、制度に振り回されないコト
(助成金は手段であり目的ではない)が大切だと考えています。
○業務・採算の見える化、業務改善
会社は知らずのうちに儲からなくなっていくものと言われます。
そこで重要なのが、業務・採算の見える化と業務改善です。
まずは自社にどんな業務が存在しているのか、仕事の棚卸しを行います。
それと合わせて、誰がどんな仕事をできるかというスキルを整理することが肝要です。
次は、商品・サービス別の採算を数字で把握することです。
単に「売上」だけを見ていても実態は分かりません。
重要なのは、粗利益を労働時間で割った《時間当たり採算》を出すことです。
例えば、同じ粗利益100万円でも、
・50時間で達成した案件は「時給2万円」
・200時間かかった案件は「時給5千円」
となり、生産性は大きく違います。
この数値を出すと、思いがけない発見があります。
「売上が大きいと喜んでいた取引が、実は時間効率が悪くて赤字に近い」
「小規模な仕事だと思っていたものの方が、実は高収益だった」
そんなケースは決して珍しくありません。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
長期目線で考える企業の対応
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
○給与設計の見直し
最低賃金が上がり続けるなか、給与設計をそのままにしておくと、いずれ矛盾が生じます。
「入社3年目の社員と、新入社員の給与が並んでしまう」
「下の層の引き上げが上の層に波及し、全体が歪む」
こうした現象が起こってくるのではないでしょうか。
ここで考えたいのは、どんな人に働いてもらいたいか
また、どんな人を評価したいか、どんな人を採用したいかで考えていくことです。
給与設計は会社からのメッセージであるといえます。
それを踏まえて何年かに一度、等級制度や昇給カーブ、手当など見直すことも有用です。
○事業構造の転換
最低賃金が上がり続ける社会においては、
採算がとれるビジネスモデルを構築しなければなりません。
低価格競争に巻き込まれないようにすることが、
ここでは重要ではないでしょうか。
価格を下げてシェアを取りに行くモデルは、最低賃金の上昇と真っ向から衝突します。
これは「人件費が上がればすぐに採算が崩れる」構造を持っているからです。
これからは、「安さ」ではなく「独自性・付加価値」で選ばれる
商品・サービスへと転換する必要があります。
また、同時に顧客と市場について、
誰にどういう価値を届けていくかというのを改めて考えてみても良いかもしれません。
どういうお客さんにどういう商品を売るかを考えるキッカケにしている会社もありました。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
まとめ
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
最低賃金が上がり続けることは、ほぼ避けられないと思います。
その対応策として、短期的には、
助成金の活用や業務・採算の見える化、業務改善で足元を固め、
長期的には給与設計の見直しや事業構造の転換で
未来を描くことが求められると考えています。
「最低賃金の上昇に耐えられるかどうか」ではなく、
「最低賃金の上昇をどう成長のきっかけにするか」
この問いに向き合える会社こそが、次の時代にも成長する企業になるのではないかと思います。
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 岸田 飛生
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【E-Mail】support@4jh.jp
【電 話】06-6945-5550
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー